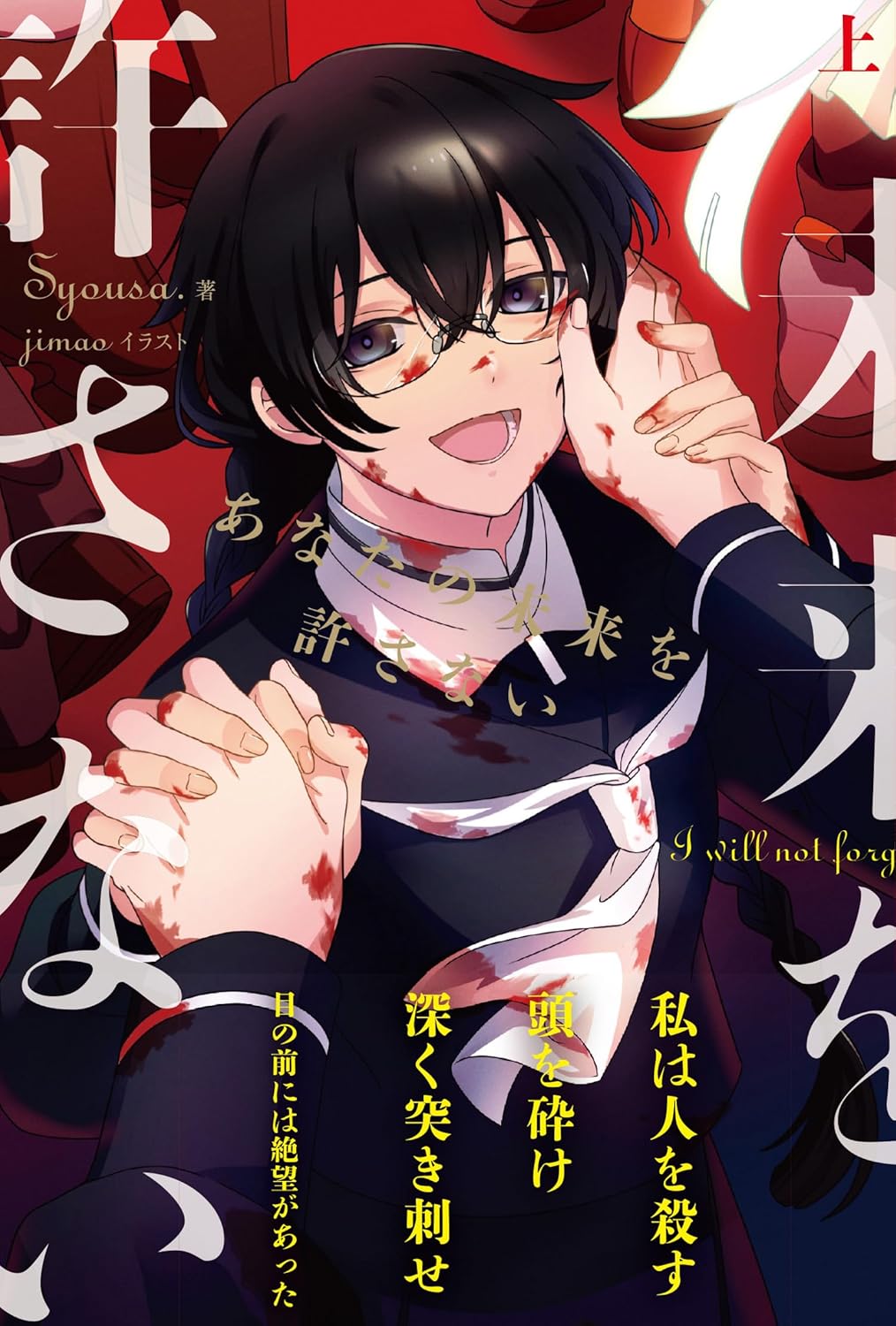オールタイムベストって「自分が好きな作品」を選ぶか「客観的に重要な作品」を選ぶかでかなり性質が違ってくると思うんですが、そもそも「自分が好きな作品」なら毎年の個人的ベスト10をまとめればいいだけだし、「客観的に重要な作品」を選ぶならアニメ化リストを見ながら売れてそうな作品を選ぶだけなので、あんまり面白くないんですよね。
と思いつつ、まあ何事も経験だし、いったん100作品挙げてみるか、ということでリストアップしてみました。大変でした。
いや100作品って中途半端なんですよ。まずパッと思いつく作品を並べてみたら60作品くらいだったんですよ。んで気合を入れて候補をリストアップしたら140作品くらいになったわけですよ。だからもう極端に言えば「同率61位が80作品ある」みたいな感じなんですよね。今日寝て明日起きたらぜんぜん別のリストを作っているかもしれない。その程度のものです。
ちなみに私がリアルタイムで知っているのはだいたい2000年以降です。それ以前の作品は、先達のラノベ語りを聞いて、そこでよく出てくる作品とかを並べているだけだと思ってください。
あと、個人的な信条として、少女向けやライト文芸も含め、ラノベの定義をなるべく広く取ろうとしています。
なろう系は本当に網羅しようと思ったら数が多すぎるので「悪役令嬢」とか「追放もの」とか「クラス転移」とか「グルメもの」とかそういった小ジャンルの代表を選んでいるような感覚です。
もっと「自分が好きな作品」も入れたかったんですが、どちらかというと「客観的に重要な作品」だけで一杯になってしまっています。
そういった意味でも、全体的に選出基準にムラがあって、かなりバランスが悪いリストだと思っているんですが、リスト作成に費やした時間がもったいないので記事にします。このリストが完璧だとはまったく思っていません。と言い訳しまくっておきます。
というわけでそのリストです。
- 時をかける少女(1967年)
- ウルフガイ(1971年)
- ねらわれた学園(1973年)
- クラッシャージョウ(1977年)
- グイン・サーガ(1979年)
- 星へ行く船(1981年)
- 銀河英雄伝説(1982年)
- キマイラ(1982年)
- 吸血鬼ハンターD(1983年)
- なんて素敵にジャパネスク(1984年)
- 妖精作戦(1984年)
- ロードス島戦記(1988年)
- 隣り合わせの灰と青春(1988年)
- フォーチュン・クエスト(1989年)
- スレイヤーズ(1990年)
- 炎の蜃気楼(1990年)
- ゴクドーくん漫遊記(1991年)
- 蓬萊学園シリーズ(1991年)
- 〈卵王子〉カイルロッドの苦難(1992年)
- 十二国記(1992年)
- 魔術士オーフェン(1994年)
- セイバーマリオネットJ(1995年)
- タイム・リープ(1995年)
- ブラックロッド(1996年)
- ブギーポップシリーズ(1998年)
- マリア様がみてる(1998年)
- フルメタル・パニック!(1998年)
- ラグナロク(1998年)
- 皇国の守護者(1998年)
- キノの旅(2000年)
- まるマシリーズ(2000年)
- 少年陰陽師(2001年)
- まぶらほ(2001年)
- トリニティ・ブラッド(2001年)
- イリヤの空、UFOの夏(2001年)
- 古典部シリーズ(2001年)
- 戯言シリーズ(2002年)
- GOTH(2002年)
- NHKにようこそ!(2002年)
- 灼眼のシャナ(2002年)
- 伝説の勇者の伝説(2002年)
- 涼宮ハルヒシリーズ(2003年)
- 撲殺天使ドクロちゃん(2003年)
- 彩雲国物語(2003年)
- 半分の月がのぼる空(2003年)
- 銀盤カレイドスコープ(2003年)
- されど罪人は竜と踊る(2003年)
- マルドゥック・スクランブル(2003年)
- 空の境界(2004年)
- ゼロの使い魔(2004年)
- とある魔術の禁書目録(2004年)
- 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない(2004年)
- All You Need Is Kill(2004年)
- レイン(2005年)
- 狼と香辛料(2006年)
- とらドラ!(2006年)
- “文学少女”シリーズ(2006年)
- 図書館戦争(2006年)
- バカとテストと召喚獣(2007年)
- ミミズクと夜の王(2007年)
- 俺の妹がこんなに可愛いわけがない(2008年)
- 生徒会の一存(2008年)
- とある飛空士への追憶(2008年)
- AURA 〜魔竜院光牙最後の闘い〜(2008年)
- ソードアート・オンライン(2009年)
- IS〈インフィニット・ストラトス〉(2009年)
- 紫色のクオリア(2009年)
- まおゆう魔王勇者(2010年)
- ゲート(2010年)
- 悪ノ娘(2010年)
- 魔法科高校の劣等生(2011年)
- やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。(2011年)
- デート・ア・ライブ(2011年)
- ビブリア古書堂の事件手帖(2011年)
- 魔弾の王と戦姫(2011年)
- 冴えない彼女の育てかた(2012年)
- オーバーロード(2012年)
- ニンジャスレイヤー(2012年)
- この素晴らしい世界に祝福を!(2013年)
- ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(2013年)
- 青春ブタ野郎シリーズ(2014年)
- Re:ゼロから始める異世界生活(2014年)
- 転生したらスライムだった件(2014年)
- 無職転生(2014年)
- 薬屋のひとりごと(2014年)
- 異世界居酒屋「のぶ」(2014年)
- ようこそ実力至上主義の教室へ(2015年)
- りゅうおうのおしごと!(2015年)
- 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…(2015年)
- ありふれた職業で世界最強(2015年)
- 君の膵臓をたべたい(2015年)
- ゴブリンスレイヤー(2016年)
- 弱キャラ友崎くん(2016年)
- 86-エイティシックス-(2017年)
- 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました(2018年)
- お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件(2019年)
- わたしの幸せな結婚(2019年)
- 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん(2021年)
- VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた(2021年)
- 誰が勇者を殺したか(2023年)
おまけで、リストからは泣く泣く外したけれども「自分が好きな作品」寄りの候補。
未アニメ化の定番名作。このラインの作品をリストアップしたほうが面白いのでは?と思わないでもない。
- ROOM NO.1301(2003年)
セックスあり青春ラノベの代表格。
- 白い花の舞い散る時間(2005年)
最近思い出す機会があった。刊行当時にかなり話題になった鮮烈な作品。こういうのも入れたいよな。
ラノベにおける「無双」「俺TUEEE」の先駆けとしてエポックメイキングな存在だと思っている。
- ぼくと魔女式アポカリプス(2006年)
- 空色パンデミック(2010年)
ある種の極北として非常に重要な作品だと思っているが同意が得られないのも理解している。
- 幽霊列車とこんぺい糖(2007年)
砂糖菓子を入れるならこんぺい糖も入れたいじゃないですか。
- 迷宮街クロニクル(2008年)
2008年にすでに最高の現代ダンジョンものが出ていたという事実を噛み締めたい。
- 僕は友達が少ない(2009年)
「日常系ラノベ」で選ぶならジャンルを確立した『生徒会の一存』は外せないんだよな、と思ってこっちを外しました。すみません。
- ヴァンパイア・サマータイム(2013年)
やっぱり石川博品は入れておくべきなんじゃないですか。
- 継母の連れ子が元カノだった(2018年)
- ひげを剃る。そして女子高生を拾う。(2018年)
2010年代後半からのラブコメブームの初期の代表格として入れておくべきなのではと悩む。